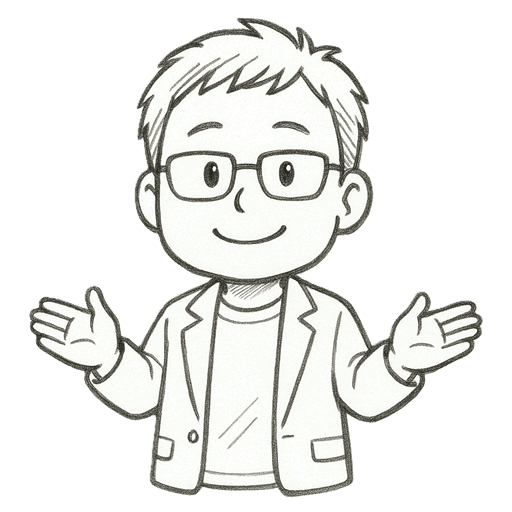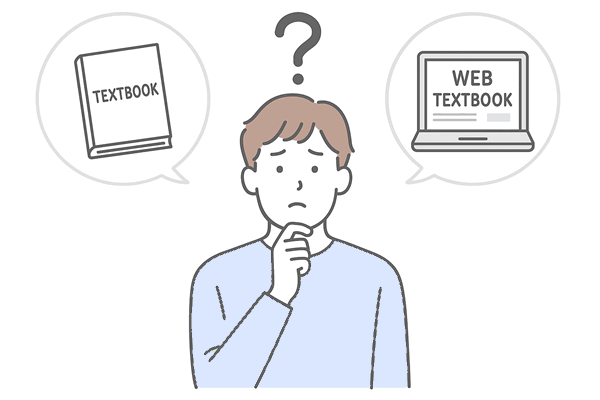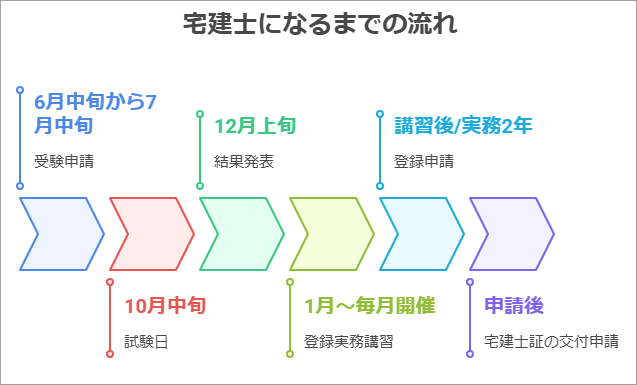
どうも宅建士のけんまるです。
私は1年かけて宅建に合格したのですが😅 「勉強に時間をかけられない」「直前期から一気に仕上げたい」 という人は多いはずです。
実際、宅建は出題範囲が広いものの、効率的に学習すれば 3か月〜半年の短期合格 も十分に可能な資格です。
特に最近の宅建通信講座は、要点を絞ったカリキュラムやスキマ時間学習に対応したアプリが充実しており、忙しい社会人や学生でも短期間で合格レベルに到達できる環境が整っています。
この記事では、
- 短期合格に必要な勉強時間の目安
- 3か月・半年で勝負できるおすすめ宅建通信講座
- 短期合格を狙う人の勉強スケジュール例
をまとめて解説します。
「急に思いついた宅建士、短期集中で受かりたい!」という方は、ぜひ参考にしてください。
宅建は短期合格できる?必要勉強時間の目安
宅建試験の合格に必要とされる勉強時間は、一般的に300時間〜400時間 と言われています。
これは「1日2時間×半年」あるいは「1日3〜4時間×3か月」といったペースで到達できるボリュームです。
もちろん、法律の学習経験や暗記の得意不得意によって前後しますが、
半年で合格を狙うなら:1日1〜2時間(平日中心でもOK)
このような学習ペースが目安になります。
短期合格を実現するために大切なのは、「出題頻度の高い分野を優先する」ことです。宅建試験は出題範囲が広いものの、実際には民法・宅建業法・法令上の制限といった主要科目で得点の大半が決まります。
そして毎年の試験内容は、過去の焼き直しが多くを占めているのです。
通信講座を活用すれば、これらの分野を効率よくインプット・アウトプットできるように設計されているため、短期間でも合格ラインを狙うことが可能です。
つまり、宅建は「時間をかければ必ず受かる資格」ではなく、「必要な範囲を効率よく学べば短期でも十分チャンスがある資格」と言えます。
3か月合格を狙える宅建通信講座【厳選】
「3か月で宅建合格」というのは、かなりタイトなスケジュールです。
ただし、効率的なカリキュラムを選べば、短期集中で合格ラインに届く可能性は十分あります。
ここでは、特に 要点を絞ったカリキュラム・スマホ学習・過去問演習の効率化 に強みを持つ通信講座を厳選しました。
スタディング宅建講座

- スマホ完結型で、スキマ時間を徹底活用できる
- 短期集中の「学習フロー」が用意されており、インプット→問題演習を最速で回せる
- 倍速再生・学習マップなど、短期学習に特化した設計
👉 3か月で一気に仕上げたい社会人・学生に最適。
フォーサイト宅建講座

- フルカラーテキスト&図解で、短期間でも理解がスムーズ
- 問題集の的中率が高く、無駄のない出題範囲で効率良く学習できる
- eラーニングで、動画学習と過去問演習をスマホからサクサク
👉 短期間でも合格を確実に狙いたい人向け。
アガルート宅建講座

- 「直前対策カリキュラムや速習カリキュラム」で短期合格に対応
- 講師の講義が要点集中型でインプットが非常に速い
- 合格特典(受講料全額返金・お祝い金)もあり、モチベ維持に強い
👉 最速で合格を目指しつつ、保証制度も欲しい人におすすめ。
半年で合格を目指す人におすすめの講座
宅建試験に向けて 半年(6か月)前から準備する のは、もっとも現実的かつ合格率の高い学習パターンです。
1日あたり1〜2時間の学習を積み重ねれば、必要な300〜400時間を無理なく確保できるため、社会人や主婦、学生など幅広い層に適したスケジュール といえます。
半年合格を狙う場合は、インプットとアウトプットのバランスがとれた講座を選ぶことが重要です。以下の通信講座は、無理なく続けられるカリキュラムとサポート体制 に強みがあります。
ユーキャン宅建講座

- 分かりやすいテキストと添削課題があり、コツコツ学習に強い
- 添削や質問サポートで「継続して勉強できる仕組み」が整っている
- 初心者でも半年計画で十分合格が狙えるスタンダード講座
👉 じっくり勉強を進めたい初心者におすすめ。
クレアール宅建講座
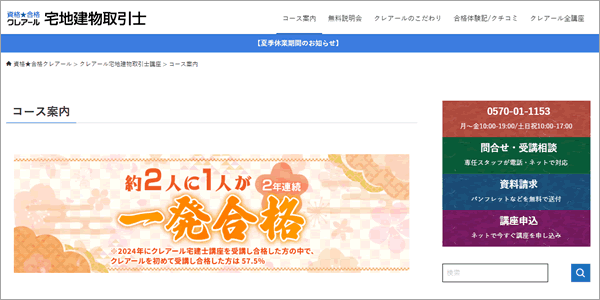
- 「非常識合格法」で有名。出題範囲を徹底的に絞り、学習効率を高める
- 半年スケジュールでも、無駄のない学習が可能
- 価格も比較的安く、費用を抑えたい人に人気
👉 半年で効率よく得点力をつけたい社会人に最適。
LEC宅建講座

- 通信+通学のハイブリッド学習が可能
- 大手ならではの教材と過去問分析力で安定感がある
- 半年間かけて体系的に学びたい人にぴったり
👉 安心感と網羅性を重視する人におすすめ。
📌 まとめ
半年の学習期間を確保できるなら、
効率重視・費用を抑えたい → クレアール
大手の安心感・万全体制 → LEC
このあたりが候補になります。
半年あれば、インプット→過去問演習→直前模試と、余裕を持ったスケジュールで合格レベルに到達できます。
短期合格の勉強法とスケジュール例
短期で宅建に合格するには、勉強時間を確保すること以上に「優先順位をつけた学習」が不可欠です。宅建試験は出題範囲が広い一方で、頻出分野を押さえるだけで合格点に届く仕組みになっています。
短期合格のポイント
💡宅建業法を最優先に学習(全50問中20問。高得点源)
💡法令上の制限を次に重点化(8問。覚えやすく得点効率が高い)
💡民法・その他科目は頻出論点に絞る(すべて網羅せず、頻出テーマ中心)
💡過去問演習を繰り返す(新しい問題に手を広げるより過去問重視)
💡アウトプット比率を増やす(短期は特に「解いて覚える」が効果的)
3か月合格を狙うスケジュール例
1か月目:インプット中心
宅建業法・法令上の制限の基本を動画講義+テキストで学習
2か月目:アウトプット開始
過去問を科目別に解き、理解が浅い部分を重点復習
3か月目:総合演習&模試
本試験形式で模試を繰り返し、時間配分と弱点補強
👉 1日3〜4時間(休日は5時間以上)の学習が前提。
半年合格を狙うスケジュール例
1〜2か月目:基礎固め
各科目をバランスよくインプットし、簡単な問題に触れる
3〜4か月目:過去問徹底
宅建業法・法令上の制限を重点に、過去問演習を繰り返す
5〜6か月目:直前対策
模試や予想問題集で仕上げ。苦手科目は重要論点だけ絞って復習
👉 1日1〜2時間のペースでも無理なく到達可能。
短期合格を成功させるコツ
☑毎日学習を途切れさせない(短期は継続で記憶を維持することが命)のが超重要!
☑通信講座の学習スケジュールを活用する(無駄な計画立てを省け、かつそれ以上のペースで進む)
☑直前期は模試を最優先(得点力を一気に高める)
2か月で宅建合格を目指す可能性について
「宅建に2か月で合格できるか?」という疑問を持つ方も少なくありません。結論から言うと、2か月合格は非常に難易度が高いものの、不可能ではありません。
宅建試験の合格に必要な勉強時間は 300〜400時間程度 とされます。
これを2か月で確保しようとすると、1日5〜6時間以上の学習ペース が必要です。社会人や学生にとっては現実的にかなり厳しいスケジュールですが、状況によっては挑戦する価値があります。
2か月合格が狙える条件
☑まとまった学習時間を毎日確保できる(1日5時間以上)
☑出題頻度の高い分野に徹底的に集中できる
☑通信講座の速習カリキュラムを利用し、最短ルートで学習できる
学習戦略の例
1か月目:宅建業法と法令上の制限に学習を集中(得点源を固める)
2か月目:過去問演習を徹底し、<模試形式で時間感覚を養う
民法や税・その他科目は「頻出論点のみに絞る」ことで効率化。
市販のテキストを手にすると「網羅的な学習になってしまう」ので、通信講座の直前対策系コースを受講するのが近道です。
だいたい8月~9月にかけて、大手通信講座では新たなコースが提供されはじめますので、そこをチェックしておくことですね。
2か月合格は万人向けではなく、「相当の集中力と学習経験がある人向け」です。「どうしても今年合格したい」「直前期から一気に仕上げたい」という人は費用をかけて近道ルートに進みましょう。
まとめ(短期で狙うならこの通信講座が鉄板)
宅建試験は学習範囲が広い資格ですが、効率的に学習すれば3か月〜半年の短期合格も十分に可能です。
大切なのは、闇雲に勉強するのではなく、「頻出分野を優先」「過去問を徹底」という王道戦略を、無駄のない通信講座で実践することです。
本記事で紹介したように、短期合格に強い通信講座は以下の通りです。
3か月合格を狙う人
☑スキマ時間をフル活用できる → スタディング
☑効率的かつ的中率重視 → フォーサイト
☑短期速習カリキュラム+返金制度あり → アガルート
半年合格を狙う人
☑基礎からじっくり積み上げたい → ユーキャン
☑出題範囲を絞って効率重視 → クレアール
☑大手の安心感で確実に進めたい → LEC
短期合格を本気で目指すなら、自分に合った通信講座を選び、用意されたカリキュラムに沿って淡々と学習を進めるのが最も近道です。
「今年こそ宅建に受かりたい」「できるだけ短期間で決着をつけたい」という方は、ぜひ本記事で紹介した講座から選び、最短ルートで合格をつかみ取りましょう。
短期じゃなくてもいい、来年合格を目指す選択肢
宅建試験を調べていると「3か月で合格!」「最短2か月で一発合格!」といったフレーズをよく目にします。確かに短期集中で合格を勝ち取る人もいますが、全員が同じペースで勉強できるわけではありません。
仕事や家事、育児で忙しい人にとっては、毎日長時間の勉強を確保するのは現実的に難しいもの。そうした場合、「無理に短期合格を狙わず、来年の試験をゴールに設定する」という選択肢も立派な戦略です。
来年合格を目指すメリット
💡学習ペースを自分の生活リズムに合わせられる
💡基礎をじっくり固められるため、知識が定着しやすい
💡直前期に焦らず、計画的に仕上げられる
💡モチベーションの維持がしやすい
宅建試験は毎年実施される国家資格です。1年かけてじっくり準備しても何の問題もなく、むしろ「生活に無理なく勉強を取り入れる」ことが長期的に合格への近道になることもあります。
どうしても今年中に宅建士になって、不動産業界へ転職したい?
宅建士の求人を見ると、「月給50万」とか「年収600万」といった数字が見られる場合があります。それで宅建士になる意欲が湧くと思うのですが、現実は、そんな求人滅多にないよ、ということなんです。自分も求人サイトの罠にハマった側なので、そのことを伝えないのはよくないと思いまして。
現実には宅建士だけでは年収600万払う会社はありません。不動産会社の「営業マン兼宅建士」の話です。宅建士の事務職の給与は時給1500円がいいところです。リーガルチェックができる経験者なら、都内で月給35万円ぐらいの求人が出てると思いますが。
それ以外は営業ができないと年収は上がりませんよ。
今年こそ宅建士資格を取って、不動産業界に転職したい?
と思われてる方がいたら、転職のほうが先だと思います。資格よりも経験のほうが勝ると思います。
資格を持っていることで採用の可能性が高まるのは事実ですけど、それより「営業マン」という存在のほうが需要が高い。
資格に挑戦するのは悪くはありませんので、転職を考えているなら、合格発表を待たずに求人情報を調べたり、宅建士資格を歓迎する企業にアプローチしたりと、早めの行動 も大切です。
「受験中」「今年の試験に合格見込み」と伝えるだけでも、意欲を評価してくれる会社は多いものです。