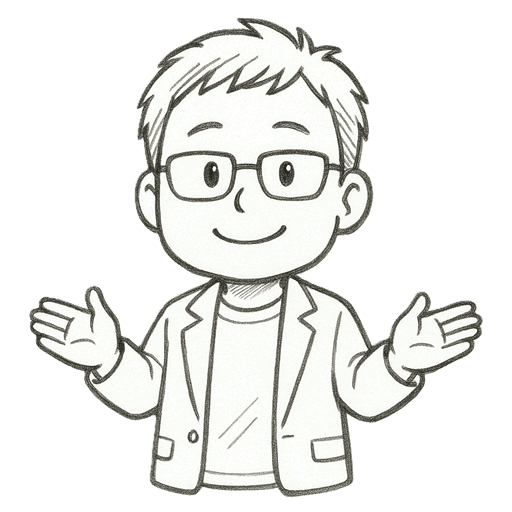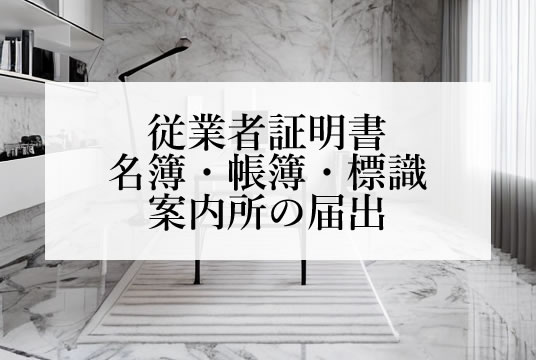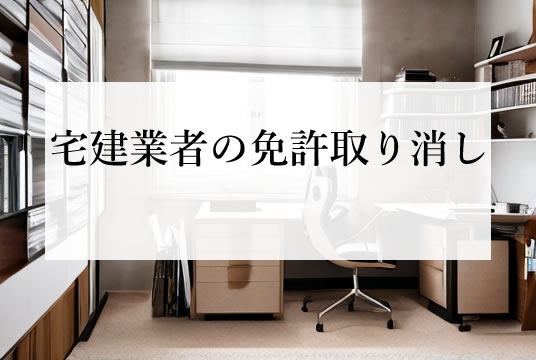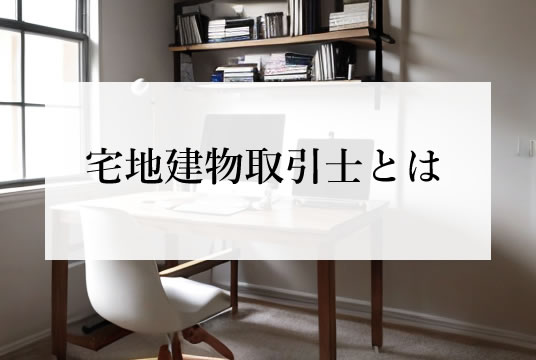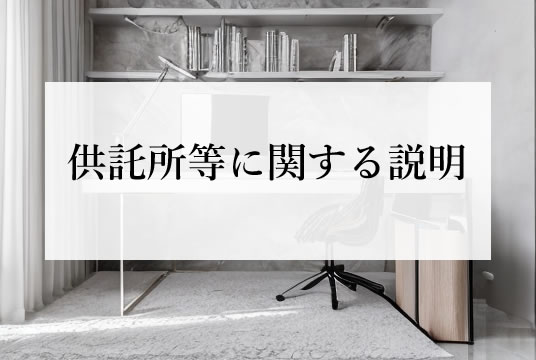このサイトは宅建試験合格を目指すために、「元情報である宅建業法をしっかり読んでおこう」というかたをサポートします。
まずは業法の条文を引用し、その後で超わかりやすい解説をいれています。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
第1項は「宅地」という用語について次のように定義しています。
>建物の敷地に供せられる土地をいい
最初の部分で、建物の敷地になる土地のことを「宅地」と定義しています。
②まだ建物は無いけど、これから建物を建てる目的で取引する土地も「宅地」として扱います。
地目や現況がなんであれ、これらに当てはまれば宅地になる訳です。
例えば、登記上の地目が畑や山林だったとしても、建物を建てる目的で取引するなら「宅地」になります。
後半の文章で都市計画法うんぬんが出てきますが、これは後で勉強する都市計画法を理解するとわかっていくことになるでしょう。
ここで簡単に説明しておくと、市町村が街づくり計画で定めた「用途地域」と呼ばれるエリア内の土地のほとんどは「宅地」になる、と言っています。(道路、公園、川など公共施設の土地を除く)
例えば用途地域にある農地や駐車場は、この法律では「宅地」として扱います。
またあとで出てきますが、都道府県が定めた市街化区域内の土地は建物を建てる予定がなくても「宅地」になりますし、市街化調整区域(積極的な街づくりをしないと定めた区域)内の土地でも建物を建てる目的なら宅地になります。
「宅地として扱う」、「宅地が適用される」とはどういうことかというと宅建業法が適用される、ということです。
・反復継続で業として売買することが目的でも宅建免許が不要ということになります
・宅建業者がこれらの土地を仲介するときの仲介手数料は3%+6万円の上限がなくなるので、宅建業者が自由に設定して手数料を受け取ることも可能です
過去問も見ておきましょう
A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。→◯
Aが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Aは、免許を必要としない。→✕
Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。→✕
📘 この分野を体系的に学べる通信講座はこちら
独学での理解が難しい法律用語や出題傾向を、動画やテキストで体系的に学びたい方は、宅建通信講座の比較ページをご覧ください。主要6講座(アガルート/フォーサイト/スタディング/ユーキャン/クレアール/LEC)を、合格率・料金・サポート体制などでわかりやすく比較しています。