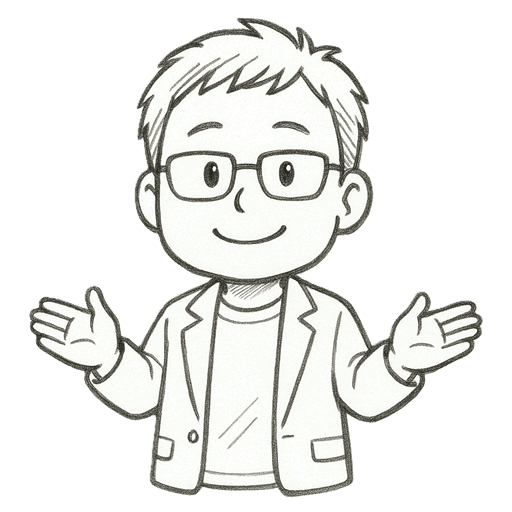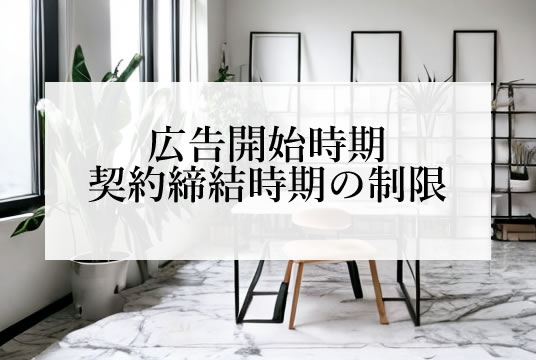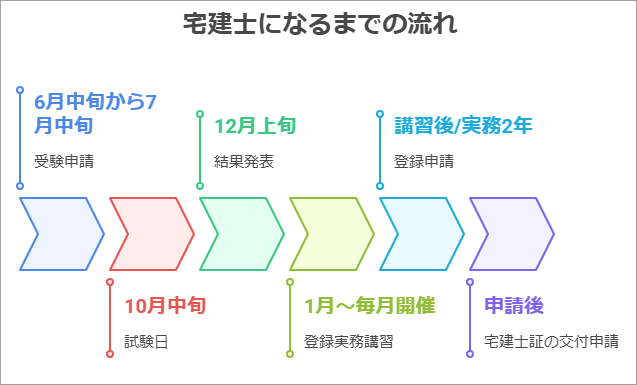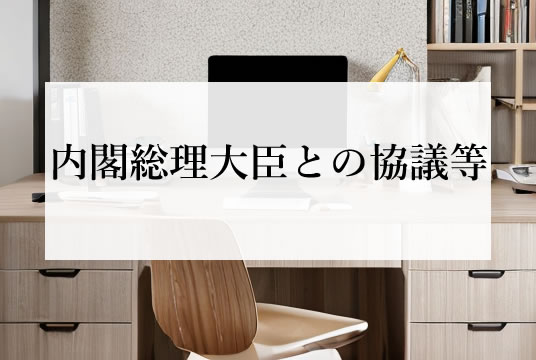ちょうど宅建試験の出題範囲(2025年4月1日施行まで)に入っているのが、2025年4月1日施行の建築基準法です。
その中で特に試験で狙われそうなのが、「建築確認」に関する部分です。
改正前から改正にいたる主旨
まず、何故変わったのかを把握しておくと、背景と相まって記憶に残りやすいです。(参考:改正建築基準法についてのPDF)
日本の「建築基準法」では、家やビルなどの建物を建てるときに、守らないといけない決まりがあります。
① 工事を始める前と終わった後のチェックがある
ふつうは、建物を建てる前に「この設計で本当に大丈夫か?」という「建築確認」を受けて、工事が終わった後にも「ちゃんとルールどおりに完成したか?」という「完了検査」を受ける必要があります。(大規模な建物の場合は中間検査もある)
場所や建物の大きさによっては建築確認が必要ないことがあります。都市から離れた田舎など「都市計画区域の外」にあるエリアでは、小さな建物については、この確認や検査が不要でした。
②また、都市の中でも一部の検査が省略されることがあります。
「都市計画区域の中」では、小さな建物で建築士が設計して工事監理をしている場合は、一部のチェック(特に建物の強さなど)を省略してもよいという特別ルールがあります。
最近は、省エネな建物が増えてきていて、それに伴って建物が重くなることもあるので、審査を通して地震などでも倒れないように強く作ることが大切です。住む人が安心して家を建てたり買ったりできるようにする必要があり、今回の改正に至ったと言えます。
改正建築基準法(2025年4月施行)の内容
宅建試験に向けては、表を見てもらったほうが早いと思いますので、こちらをご覧ください。
建築確認が必要な建物の表です。
2024年までの宅建試験勉強より、明らかに暗記が簡単になっています。
| エリア | 建築物の種類 | 新築 | 増築 改築 移転 |
大規模修繕 大規模模様替 |
用途変更 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 200㎡超の特殊建築物★1 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
| 1.階数が2以上 2.延べ面積200㎡超 1か2どちらかを満たすもの★2 |
必要 | 必要 | 必要 | 不要 | |||
| 都市計画区域 準都市計画区域 準景観地区 |
【内】★3 | 平屋かつ200㎡以下 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | |
| 平屋かつ200㎡以下★4 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |||
★5※防火地域及び準防火地域【外】→増築・改築・移転で、床面積合計が10㎡以下→不要
注釈の解説と要点ポイント
星印をつけた部分について注釈を入れましたので、表とあわせてご確認ください。
★1:これは建築基準法6条1項1号の建物です。
「特殊建築物」とは何かというと、学校、体育館、病院、劇場、集会場、展示場、旅館、向上、倉庫、、、などがあります。
用途変更に関しては、建築物の用途を変更して、200㎡超の特殊建築物に変更する場合も建築確認が必要です
→逆に言えば、特殊建築物以外にする場合は建築確認が不要。
→また類似用途への変更の場合は、建築確認は不要です。(例:劇場→映画館、ホテル→旅館、カフェ→バー)
特殊建築物で類似の用途とは何かというと「建築基準法施行令第137条の18」に記載があります。
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
★2:これは建築基準法6条1項2号の建物です。
2階以上または延べ面積200㎡超の建物で、木造、鉄骨造など無関係です。
一般的な2階建て住宅もこれに該当するようになりました。
新築・増改築移転はもとより・大規模修繕でも建築確認が必要になります。
★3:これは建築基準法6条1項3号の建物です。
1号2号を除き、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区【内】にある建物が該当します。
なので、平屋で200㎡以下のコンパクトな家は、新築・増改築移転→必要。大規模修繕→不要となっています。
★4:これは建築基準法には規定されていませんが、これまでの規定に当てはまらない、
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区【外】、つまり田舎で、平屋で200㎡以下のコンパクトな家は、すべて不要になります。
★5:これはつまり、防火地域・準防火地域【内】なら必ず建築確認が必要ということです。
そして、防火地域・準防火地域【以外】で、【増築改築移転】が10㎡以下なら建築確認不要ということです。
参考:木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について
こちらも参考:環境省エネルギーセンター
結局これはどういうことなのか、不動産屋はどうすればよいか
宅建士や不動産屋として重要なのは「重要事項になりえるので買主に説明しないといけない」ということにつながります。
過去新築時には建築確認・完了検査が不要だった→大規模修繕時に建築確認が必要になる?
→ 真実です。
📝4号特例の縮小
従来、「4号建築物」(木造2階建て以下など)では、設計図書通りに建築士が設計・確認すれば、構造関係の審査(建築確認)は省略可能でした(いわゆる「特例」) 。
🆙改正後の扱い
2025年4月1日施行の改正により、4号特例の対象は縮小され、多くの戸建てが「新2号建築物」に分類され、大規模リフォーム時に建築確認申請が必要となりました。
「主要構造部」(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の過半(2分の1を超える)改修が行われる場合は、大規模修繕とみなされ、建築確認申請が必須です。
したがって、「新築時には確認が不要だったが、大規模修繕では必要になる」という課題が存在するようになってしまいました。。
検査済証や設計図書等がないと、大規模修繕時に建築確認ができない?
→ これは部分的に正しく、代替手段があります。
中古住宅などで 検査済証や設計図書が存在しない場合、そのままでは建築確認申請が進められません。ただし、代替的な証明手段が用意されています。
自治体で「当時確認申請・検査済が行われたかどうか」を履歴として確認する証明書です。
指定確認検査機関による現況調査で、建物が法令に適合している状態であることを示す報告書です。これを添付することで確認申請の代替となり得ます。
ただし、検査済証のような「正式な完了検査済み」の証明ではないため、追加の補強や設計調整が必要となるケースも多い点には注意です。
そして費用がかかる点も課題で、数万円~数十万円とされ、建物規模や調査範囲によって変動します。
補足情報
専門家や相談窓口の利用:自治体や建築士会、指定確認検査機関などによる相談・サポート体制が全国で整備されています。→国土交通省
不動産屋・宅建士としての説明責任
売買時の説明が増えることになります。中古住宅の買主には重要事項説明書に「設計図書や検査済証の有無」が記載されますが、ない場合に何が起こるか(増改築や大規模修繕ができないなど)も説明することになるでしょう。
改正建築基準法(令和7年4月1日施行)重要事項説明書の書き方例
建築確認済証が無いとか、検査済証が無いとか、設計図書がない場合は、特約に記載しておくことがリスク回避になると思います。
※この部分に関しては筆者も調査中です。勤めてる不動産屋や保証協会にも確認中ですので後日更新します。
ったく難しすぎるんだよぉ・・・(´・ω・`)